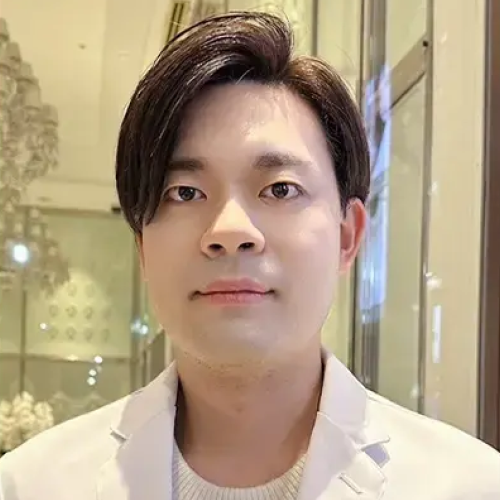爪を抜く「抜爪」と呼ばれる施術は、ほかの方法では改善が見られない場合の最終手段として行なわれる医療行為です。
この記事では「どんなときに爪を抜くのか」4つの主な症状について解説。抜爪したあとの回復経過や再発を防ぐための予防法、自分で爪を抜く行為が危険な理由をまとめました。
爪を抜く必要がある状態とは?4つの主な症状
爪は日常生活で非常に重要な役割を果たしており、通常は安易に抜くことはありません。
しかし下記のように大きな怪我や感染症、変形などによってほかの方法では改善が見込めない場合は、最終手段として抜爪手術が行なわれます。
①爪が分厚く変形したとき
爪が分厚く変形した状態を「肥厚爪」と呼びます。
爪が分厚くなるのは「爪白癬」という真菌(カビ)の感染症が主な原因です。初期には爪が白や黄色に変色します。
そのほかにも加齢による血行不良や、靴の圧迫などによる慢性的な刺激が要因となることがあります。特に、小さすぎる靴や、足先に負担がかかるような歩き方を続けると、爪が繰り返し刺激され、防御反応として厚くなっていくため注意が必要です。
通常なら爪の表面を削ったり抗真菌薬を塗布したりすることで改善が見込めますが、薬が浸透しないほどの厚みがある場合や激しい痛みを伴う場合は爪を根本から取り除く抜爪が必要になることがあります。
爪を剥がすことで爪床に直接薬を塗布しやすくしたり、新たな爪が健康に生え変わるように促したりするのが目的です。
②巻き爪・陥入爪が悪化したとき
巻き爪は遺伝的な体質やサイズが合わない靴による圧迫、深爪などの不適切な爪の切り方が原因で起こりやすいトラブルです。さらに悪化すると爪が皮膚に深く刺さり込み、「陥入爪」に進展することがあります。
軽度ならワイヤーやプレートを使った矯正や食い込んでいる部分だけを部分的に切除する手術で改善が可能。しかし、炎症や感染症の症状が酷く、肉芽が大きくなりすぎて爪の食い込みを解消できない場合には抜爪になる可能性があります。爪を抜くことで炎症を起こしている爪床の改善を促すのが目的です。
③爪の下で重度の感染症が見られるとき
爪の下に感染症が起こることを「爪下感染」と呼びます。これは、糖尿病や免疫力の低下している人によく見られる症状です。
進行すると発熱や倦怠感など全身の症状を伴い、骨髄炎など深刻な状態に発展するリスクもあります。
軽度の感染症であれば、抗生物質の内服や外用薬で改善を促すことが可能です。しかし、膿が爪の下に溜まってしまい、外からでは排出できない場合や感染が骨にまで達している恐れがある場合は、爪を抜いて膿を出す必要があります。
抜爪によって感染部位を直接洗浄・消毒し、原因菌を特定して適切な施術を行うのが目的です。
④爪が怪我などで剥がれてしたとき
怪我や事故によって外部から強い衝撃が加わると、爪の一部または全体が意図せず剥がれることがあります。
感染するリスクが高い場合や爪の下に大きな血腫ができて激しい痛みを伴う場合に抜爪が検討されます。不安定な爪をそのままにしておくと、さらに剥がれて爪床を傷つける可能性が高くなるためです。
手術で古い爪を完全に除去し、傷をきれいに洗浄することで、新しい爪が正しく生え変わるための土台を作ります。
爪を抜いた後はどうなる?回復の流れと注意点
爪を抜くと指先はどのような経過をたどるのか。新しい爪が生え変わるまでの期間や日常生活での注意点についてまとめました。
爪が生え変わるまでの期間
爪は根元にある「爪母」という部分で作られていきます。ここで新しい細胞が押し出されるように前へ前へと伸びていくため、完全に先端まで生えそろうにはかなりの時間が必要です。
手の爪はおよそ半年ほどで生えそろい、1日にわずか0.1mmほどずつ伸びていきます。これに対して足の爪は伸びがゆっくりで、完全に戻るまでに1年から1年半ほどかかるのが一般的です。
さらに、爪の伸びる速さは 年齢・性別・季節・活動量 などによって変動します。一般的には若い人や男性のほうが速く、また夏は代謝が活発になるため伸びが早まります。
爪が生え変わるまで長い期間になりますが、焦らず少しずつの変化を見守ることが大切です。
回復中に気をつけたいこと
爪が生えてくるまでは指先を清潔に保ち、余計な刺激を避けましょう。
清潔な状態に維持し、細菌感染を防ぐために処方された軟膏や保護材を使用します。また、入浴の際は水に長時間触れると感染リスクが高まるため、患部を濡らしてよいかどうか医師の指示を確認しておくと安心です。
再発やトラブルを防ぐケア・予防法
爪を抜くという経験は、心身ともに大きな負担となります。ただし、その後の過ごし方を正しく知り、きちんとケアを続けていけば再発を防ぐことが可能です。
爪は深爪や丸く切りすぎると、再び巻き爪や陥入爪を引き起こす原因になります。爪の端を丸めず、直線的に切る「スクエアカット」を意識しましょう。
また、靴がきつかったり先端が細すぎたりすると爪や足指に強い圧迫がかかり、再発のリスクが高まります。サイズが合っていることはもちろん、つま先に余裕がある靴を選ぶことが大切です。
そのまま放置は危険! 爪を自分で抜くのは絶対NG
爪を抜く行為は、爪と爪床を無理に引き剥がすことになります。爪床には多くの神経と毛細血管が通っており、非常に敏感です。そのため、麻酔なしで爪を剥がすことは、想像を絶するほどの激痛を伴います。
さらに、消毒されていない道具を使うと、傷口から細菌が侵入し、感染症を引き起こすリスクが高まるため非常に危険です。ほかにも、根元にある「爪母」と呼ばれる部分が傷つくと、新しい爪が正常に生えてこなかったり、形が歪んでしまったりすることがあります。
これらの根本的な原因に向き合わないまま、一時的に爪を抜いても問題は解決しません。真菌が残っていれば新しい爪も再び感染しますし、巻き爪の原因が解消されていなければ、また同じように爪が食い込んできます。悪化させないためにも、自己判断で爪抜かずに医療機関などのプロに必ず相談しましょう。
広島周辺で爪を抜くことにお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
爪のトラブルは放置すると悪化してしまうこともありますが、正しいケアや専門家による施術で改善を目指すことができます。一人で悩まず、早めに専門家へ相談することが安心への第一歩です。セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。もし現在、広島周辺で爪を抜くことにお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!