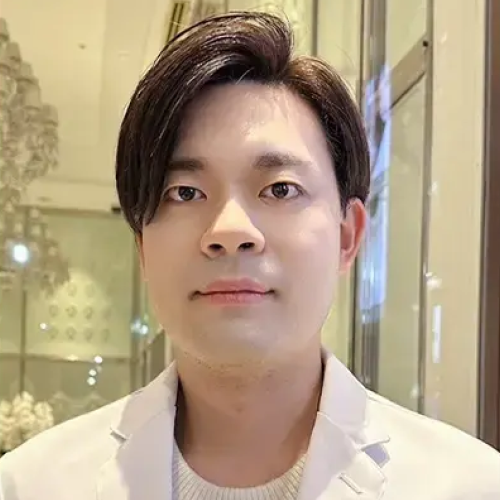爪が取れる原因は、外的な衝撃や摩擦、真菌感染、体調不良、薬の副作用など多岐にわたります。初期症状を見逃して放置すると、炎症や変形、爪母の損傷といった深刻なトラブルに発展するおそれも。
本記事では爪が剥がれる仕組みと注意すべき症状、再生の目安、そして再発を防ぐための予防習慣までを解説。手足を問わず、健康的な爪を維持するための具体的なセルフケア対策を紹介します。
爪が取れるのはなぜ?原因はひとつではない
爪が取れるとは、爪が皮膚から剥がれる現象全般を指し、一部が浮いている軽度の剥離から根元からの完全脱落まで段階があります。具体的には、以下のような症状が見られたら要注意です。
- 爪の一部が白く浮いてきて、指から離れている
- 爪の根元や側面に隙間ができ、衣類に引っかかる
- 爪が黒く変色し、押すとぐらつく・浮いている感じがする
- 爪が割れて層状に剥がれる、またはポロッと一部が取れてしまった
見た目には「一部が剥がれた程度」に感じるかもしれませんが、これは爪と皮膚の結合が少しずつ壊れている兆候です。初期の段階で適切なケアをしなければ、完全に脱落したり細菌が入り込んだりと炎症を起こすリスクも高まります。
外的な衝撃や摩擦によるもの
物理的な刺激は、爪に直接的なダメージを与える代表的な要因です。特に足の爪は、日常生活の中で知らず知らずのうちに負担を受けています。
- 指をぶつけた・挟んだ
- 足に合わない靴・長時間の圧迫
- スポーツによる継続的な刺激
- ネイルアートの影響(オフの方法含む)
- 爪の乾燥・割れやすさ
こうした外的刺激は、爪の根元にある「爪母(そうぼ)」と呼ばれる生成部分を傷つける要因になります。見た目にはわかりにくくても、内部で炎症が起こり、爪の成長が止まって剥離に至ることも少なくありません。。
爪そのものに起きている疾患
目立つ外傷がないにもかかわらず、徐々に剥がれていく場合は内部的な病変が原因の可能性が高くなります。爪の色や形が明らかに変わってきたら、次のような疾患を疑いましょう。
- 爪甲剥離症(爪が皮膚から浮いて剥がれる)
- 爪白癬(爪の水虫)
- 乾癬(皮膚の疾患が爪にも影響)
- 爪甲層状分裂症(縦に割れやすい)
- 爪扁平苔癬(免疫異常による変化)
特に爪白癬(つめはくせん)は進行が遅く、「ちょっと変色しているだけ」と思っているうちに剥がれが進行するため注意が必要です。爪の角質層内に真菌が定着すると爪は厚くもろくなり、まるで石膏のように崩れやすくなります。
体調や服薬が影響するケース
一見関係なさそうに思える体調不良や薬の副作用も、爪の脱落に深く関わっています。特に全身の代謝やホルモンバランスに関連する疾患が影響するケースは見落とされがちです。
- 貧血や甲状腺異常
- 加齢による爪の弱化
- 抗がん剤や特定の薬剤の副作用
- アレルギー・化学物質への接触
爪は「健康状態を映す鏡」ともいわれており、鉄分不足や甲状腺ホルモンの乱れは、爪の構造や成長スピードに影響を与えることがあります。抗がん剤など細胞分裂を抑制する薬剤では、爪の成長が一時的に止まり、剥がれやすくなることも。さらに、日常的に触れる洗剤・金属・ゴム手袋などが刺激源となり、接触性皮膚炎やアレルギー反応を通じて爪が浮いたり変形するケースも報告されています。
爪が取れたときにやるべき対処法3つ
爪が剥がれると痛みや出血に伴うケースがありますが、まずは落ち着いて対応することが大切です。ここでは、爪が剥がれたときにすぐ実践できる3つの対処法を紹介します。
まずは出血や浸出液の有無を確認
爪が剥がれた直後には、出血や透明な体液(浸出液)がにじむことがあります。まずは患部のようすを落ち着いて観察し、以下の点をチェックしてください。
- 出血量が多くないか
- 赤みや腫れが広がっていないか
- 傷口に汚れや異物が付着していないか
出血が軽度であれば、清潔なガーゼでやさしく圧迫し、止血を試みます。汚れがある場合は水道水でそっと洗い流し、刺激の強い消毒剤(アルコール・ヨード系)は使用を避けましょう。
痛みが長引く、浸出液が止まらない、腫れや熱感が増すといった異常がある場合は、感染や炎症が進行している可能性があります。悪化を防ぐためにも、できるだけ早く皮膚科やフットケア専門外来への相談を検討してください。
残った爪は無理に剥がさず保護
爪が部分的に剥がれたとき、残っている爪を無理に取り除くのは避けましょう。特に根元近くの損傷は、爪をつくる爪母(そうぼ)に影響を与えるおそれがあり、再生に悪影響を及ぼす可能性があります。
外的刺激や汚れの付着を防ぐため、残った爪は通気性のあるガーゼやテープで軽く覆って保護してください。湿気がこもらないようにしながら、適度な清潔を保つことが重要です。
取れた爪は捨てず必要に応じて保管・持参する
完全に剥がれた爪は、感染症や爪の変性などの有無を調べる材料として使用されることがあります。爪白癬や乾癬が疑われる場合には、顕微鏡や培養による検査に役立つことも。ただし、すべての医療機関で提出を求められるわけではないため、事前に電話などで確認しておくと安心です。保管時は、清潔なビニール袋や密閉容器を使用し、湿気や異物の混入を防ぐようにしましょう。
取れた爪はまた生える?再生の目安と注意点
爪が取れてしまったとき、爪の根元にある“爪母(そうぼ)”が無事であれば、基本的に再び新しい爪が育ってきます。爪母とは、爪を作り出す細胞が存在する組織のこと。ここが損傷を受けていなければ、時間はかかっても再生は可能です。
ただし、完全に生えそろうまでには長期間を要します。手の爪は1日約0.1mm、足の爪は月に1〜1.5mmと非常にゆっくり伸びるため、足の爪が根元から脱落した場合は半年から1年、場合によっては1年半以上かかることもあります。
注意が必要なのは、爪母自体が損傷しているケースです。爪の再生がうまく進まず、厚みや形に異常が出ることも考えられます。特に再生途中の爪は非常に繊細であり、外部からの刺激に弱いため、摩擦・圧迫・乾燥などを避けて、衛生的な状態を保つことが重要です。
自然な再生を妨げないよう、無理に削ったり整えようとせず新しい爪の成長を静かに見守りましょう。
再発を防ぐために|日常でできる予防習慣
爪がトラブルを起こすのは一度きりとは限りません。特に外的な刺激や生活習慣が関係している場合、再発を繰り返すケースも多く見られます。再び同じ悩みを抱えないためには、日常的なケアの積み重ねが不可欠です。
爪を適切な長さ・形に整える
長すぎる爪や角が尖ったままの状態は、靴の中で圧迫や引っかかりを生じやすく、剥離や割れの原因となります。深爪もまた、皮膚との密着面が減って外部刺激に弱くなりがちです。爪の先端は指先と同じくらいの長さを保ち、スクエアオフ(先端を直線に整え、角だけ軽く丸める形)を意識して整えるのが理想的です。週1回程度、ヤスリでなめらかに仕上げる習慣を取り入れましょう。
乾燥対策は手指だけでなく足指にも
肌と同様に、爪も乾燥によってもろくなります。特に足の爪は目が届きにくくケアを怠りがち。乾燥が進行すると爪が縦に割れたり層状に剥がれやすくなり、トラブルの温床になります。お風呂あがりや就寝前に、保湿クリームやキューティクルオイルで爪周囲の保湿を習慣づけることが大切です。
爪に負担をかけない靴やネイル施術を選ぶ
サイズの合っていない靴、硬すぎる素材のパンプス、通気性の悪いストッキングなどは、爪への慢性的な負担となります。特に爪先が狭い靴を履き続けると、圧迫による変形や剥離を引き起こすリスクが高まります。また、ジェルネイルやチップを長期間連続して装着するのも避けましょう。ネイルを楽しむ際は、爪の状態に応じて休息期間を設けることが重要です。
体の内側もケア・栄養・睡眠の管理も重要
爪は皮膚の一部であり、食事や睡眠といった生活の質がそのまま反映されます。特にビタミンB群の中でもビオチン(B7)は、角質の構成に深く関与します。睡眠不足やストレスも爪の成長を妨げる一因に。バランスの良い食生活と、規則正しい生活リズムを意識することが、トラブルに負けない健康な爪づくりにつながります。
広島周辺で爪が取れて困っている方はセラピストプラネットにご相談ください!
爪が取れてしまったとき、自宅でどう対処すれば良いかわからず、不安や戸惑いを感じる方は少なくありません。特に足の爪の場合、歩行や靴との摩擦によって悪化しやすく、自己判断で放置するのはリスクがあります。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。もし現在、広島周辺で爪が取れてお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!