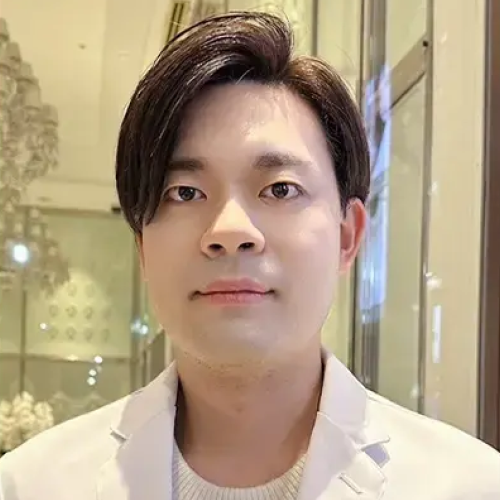深爪で爪のまわりが膿んでしまった場合、「ひょうそ」の可能性があります。細菌の感染やバリア機能の低下によって発症することがあり、早めのケアが必要になります。また、深爪にならないように予防することも大切です。この記事では、深爪から起こるひょうその原因や深爪で膿んだ時の対処法、深爪を予防する方法などについて詳しくご紹介します。
深爪で膿んだら「ひょうそ」の可能性!
指先がズキズキしたり爪のまわりが赤くなったりして気になっていませんか?それは、深爪の可能性があります。爪を短く切りすぎたり、無意識にむしってしまったりするクセがあると、小さな傷口でもそこから細菌が入り込んでしまい膿むことがあります。
この症状は「ひょうそ」と呼ばれるもので、化膿性爪囲炎(かのうせいそういえん)という病気です。単なる深爪であれば爪が伸びれば解決することがほとんどですが、ひょうそを放っておくと痛みが強くなったり、爪が変形してしまったりすることもあるため、正しい対処をする必要があります。腫れていたり熱っぽさを感じたりする場合はひょうそを疑って、なるべく早く皮膚科や当院のような爪のトラブルの専門院にご相談ください。
ひょうそ(化膿性爪囲炎)の原因は?
爪のまわりが赤く腫れて、じんじんと痛む場合、ひょうそが疑われることをご紹介しました。原因の多くは、指先にできた小さな傷口から細菌が入り込むことです。目に見えるものではないので、知らないうちに起こりやすいトラブルといえます。ここからは、ひょうその原因をもう少し詳しくご紹介します。
細菌感染
ひょうその主な原因は、細菌の感染です。皮膚は、基本的に外からの細菌やウイルスを防ぐバリアのような働きをしていますが、深爪やささくれ、巻き爪などで皮膚に小さな傷ができると、そこから細菌が侵入しやすくなります。
手荒れや爪を噛むクセ、ばんそうこうの長時間使用などで皮膚がふやけた状態も、感染リスクを高める原因です。黄色ブドウ球菌やレンサ球菌といった細菌によって炎症を起こすといわれています。赤く腫れたり、膿がたまっていたりする場合はすぐに気付けますが、あまり見た目にもあらわれないことがあるので、違和感があったら清潔を保つことを意識して、病院や当院にご相談くださいね。
バリア機能の低下
爪やそのまわりの皮膚のバリア機能が弱まることも原因です。
ネイルをする方は特にこの原因でひょうそを発症することが多く、ジェルネイルや甘皮のカット、除光液の使用などが重なると、爪の根元の皮膚がダメージを受けやすくなります。こうしたダメージにより、外部の刺激や菌が入り込みやすくなり、細菌やカビの感染が起こるのです。急性の場合は黄色ブドウ球菌やレンサ球菌、慢性的な場合はカビの一種であるカンジダが原因になることも。
ネイルをする方以外にも、水仕事が多い方は特に注意が必要です。爪のまわりが赤く腫れたり、ぷっくりと盛り上がったように見える場合は、バリア機能の低下によるひょうその可能性があります。
深爪で膿んだ時の対処法は?
深爪になった後、爪の周りがズキズキ痛んだり、膿が出てしまった経験はありませんか?膿が溜まったり出てきた場合でも、無理に膿を出すのはNGです。ここからは、深爪が膿んだ時の対処法についてご紹介します。
自分で膿を出そうとするのはNG
膿がたまっていると、指で押し出したくなるかもしれませんが、それは絶対にやめましょう。無理に膿を出そうとすると、さらに皮膚が傷つき、感染が広がる原因になります。また、傷口から別の菌が入ってしまい、炎症がひどくなることも。
小さな膿だったとしても、自分でやることにはリスクが伴います。自宅では清潔を保つことに気をつけて、早めに専門機関に相談してください。広島周辺にお住まいの方は、ぜひ当院にお任せくださいね。
次に、病院や爪のトラブルの専門院に相談する前に、自宅で行っていただきたいケアの手順をご紹介します。
①清潔な水・タオルで患部を綺麗にする
まずは患部を流水で洗い流してください。清潔なぬるま湯を使い、石けんで手全体を洗ったあと、患部もそっと洗いましょう。強くこすらず、刺激を与えないように注意してくださいね。
洗った後は、清潔なタオルやティッシュで軽く水気をふき取ります。タオルは使いまわさず、できれば毎回変えて清潔なものを使うようにしましょう。小さなことですが、清潔を保つことで感染の広がりを防ぎ、回復を早めることがあります。
②消毒液などで患部を消毒する
洗浄した後は、消毒をして細菌の繁殖を防ぎましょう。市販の消毒液(オキシドールやクロルヘキシジンなど)を使い、コットンや綿棒を使って塗布します。ピリピリする感覚があるかもしれませんが、無理に続けず、肌に合わないと感じたら使用を中止してください。
アルコール系の消毒液は刺激が強い場合もあるので、使いすぎには注意が必要です。
③ガーゼや絆創膏で患部を保護する
消毒が終わったら、ガーゼや絆創膏で患部を保護しましょう。
外出時や水仕事をする時は、汚れや外部の刺激から守るためにもカバーをするのがおすすめです。ガーゼを使う場合は通気性の良いものを選び、こまめに取り替えるようにしてください。絆創膏の場合も、長時間貼りっぱなしにせず、肌がふやけないように注意しましょう。
④病院や爪の専門院に相談する
赤みや腫れ、痛みが続いたり、膿がたくさん出たりする場合は、医療機関に相談しましょう。お困りの方は、ぜひ当院にお任せください。
当院では、深爪はもちろん、爪のトラブルに幅広く対応しております。また、深爪は単に爪を切りすぎているだけでなく、歩き方や姿勢が原因となることもあります。その場合は、体の歪みを整えて根本からの解決・再発防止を目指すために整体での施術も行っております。症状を改善するだけでなく、繰り返すトラブルを抑えたい方は、ぜひセラピストプラネットにご相談ください!
深爪を予防する方法は?
つい爪を切りすぎてしまったり、噛んでしまったりして深爪になると、痛みや炎症の原因になってしまいます。ここでは、今日からできる深爪予防のポイントについてご紹介します。
爪を切りすぎない
爪の白い部分が見えたらすぐに切ってしまっていませんか?清潔感が重視される職業の方や、楽器を演奏する方などは、短くしすぎてしまいがちです。しかし、爪の先が指の肉よりも内側まで入り込むように切ってしまうのは切りすぎと言えます。切った直後は問題がなくても、皮膚が弱って炎症を起こしたり、膿がたまる原因になることも。爪を切る時は、ほんの少し白い部分を残すくらいがちょうどいいとされています。短く切りすぎないように意識してみてください。
噛んでしまうクセがあれば噛まないようにする
爪を噛んでしまうクセがあると、気付かぬうちに深爪になってしまいます。爪を噛むクセは、ストレスを感じている人や、過集中している人によくみられます。「やめたいのにやめられない」と自分を責めてしまうと、それがストレスになり、また爪を噛んでしまう原因になってしまうことも。ストレスの発散方法を見直したり、爪を保護するネイルケアを取り入れてみたりするなど、自分にあった方法で爪を噛むクセをなくしていきましょう。
広島周辺で深爪でお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
この記事では、深爪から起こるひょうその原因や深爪で膿んだ時の対処法、深爪を予防する方法などについて詳しくご紹介しました。深爪になるとさまざまな病気のリスクになるので、爪を切りすぎないように、噛まないように気をつけましょう。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。
もし現在、広島周辺で深爪にお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!