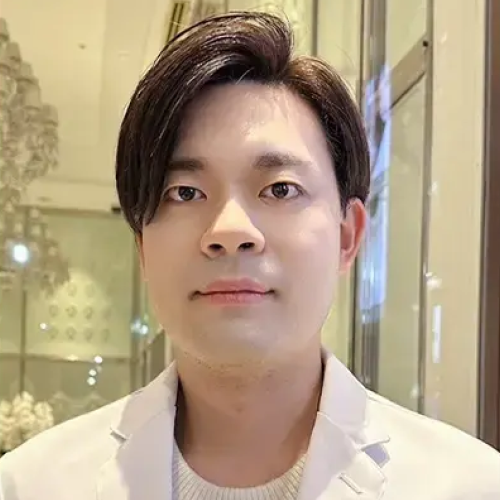爪の周りにできる角質を見過ごしがちですが、放置すると痛みや出血、感染症などのトラブルに発展することがあります。この記事では、爪周りに角質ができる主な原因と、放置した場合のリスク、さらに自宅でできるケア方法まで詳しく解説します。健康的でなめらかな指先を保つために、今日からできる対策をチェックしていきましょう。
爪周りに角質ができるのはなぜ?主な原因3つ
爪周りの角質は、皮膚を守るための防御反応として作り出されます。しかし、その防御反応が過剰になると、硬く分厚い角質に成長します。ここでは、爪周りに角質ができる主な3つの原因を見ていきましょう。
繰り返す乾燥・摩擦などの刺激
爪周りの角質化の最大の原因は、乾燥と摩擦です。
足は体重を支え、歩行のたびに地面や靴との摩擦を受けるため、手以上に角質が厚くなりやすい部位です。とくに冬の乾燥した季節や冷房や暖房で空気が乾いた室内は、皮膚の水分が失われやすくなります。乾燥が進むと肌は自らを守ろうとして角質を厚くし、硬くゴワついた状態に。
また、長時間の歩行や立ち仕事、合わない靴による圧迫、ストッキングや靴下の摩擦も角質化を招く原因です。とくに足裏やかかと、爪のまわりは負担が集中しやすく、乾燥と摩擦のダブルパンチで硬い角質がどんどん蓄積していきます。
皮膚はダメージを修復するために、古い角質を剥がすターンオーバーを繰り返します。しかし、ターンオーバーのサイクルが乱れると、剥がれ落ちるはずの古い角質が厚く硬い角質となって残ってしまうのです。
ビタミン・ミネラルなどの栄養不足
健康な爪や皮膚を保つためには、バランスの取れた食事が欠かせません。特定の栄養素が不足すると、爪や皮膚のターンオーバーが正常に行われず、角質化を促してしまうことがあります。
とくに重要なのが、ビタミンA・B群・E・タンパク質・亜鉛・鉄分です。
これらの栄養素が不足すると、乾燥やターンオーバーが乱れを招き、角質ができやすくなります。偏った食生活は爪周りの角質だけでなく、体全体の健康にも影響を与えるため、意識してバランスの良い食事を心がけましょう。
深爪などの間違った爪の切り方
「爪の白い部分をなくしたい」「短く切りすぎた方が清潔」と考えて、爪を深く切りすぎていませんか?深爪は、爪周りの角質を悪化させる大きな原因の一つです。
爪を深く切りすぎると指先の皮膚が露出してしまい、外部からの刺激を受けやすくなります。その結果、皮膚を守ろうとして角質が分厚くなってしまうのです。
また、爪の先端を丸く切りすぎると爪の両端が皮膚に食い込み、巻き爪や陥入爪の原因になります。爪は指先を保護する役割も担っているため、正しい切り方をすることが非常に重要です。
爪周りの角質を放置するとどうなる?
「ちょっとカサカサしてるだけ」と思っていても、爪周りの角質をそのまま放置するのは危険です。以下のようなトラブルを防ぐためにも、乾燥に気づいた段階で早めのケアを行いましょう。
乾燥やひび割れで出血しやすくなる
柔軟性を失った硬い角質は、乾燥するとひび割れを起こしやすくなります。
とくに乾燥しやすいかかとや爪の周りは、ひび割れが深くなると些細な刺激でも出血することもすくなくありません。さらに、開いたひび割れから雑菌が侵入すると、炎症や腫れを引き起こす可能性が高まり、健康な皮膚を脅かします。
巻き爪・陥入爪など爪の変形につながる
爪周りに硬い角質が蓄積すると爪がまっすぐ成長できなくなり、爪が内側に強く湾曲する巻き爪や、爪の先端が皮膚に食い込む陥入爪に変形する可能性が出てきます。
症状が悪化すると歩くときに強い痛みを伴い、炎症や化膿する恐れも。とくに足の親指は靴で圧迫されやすいため、角質をそのままにしておくと爪のトラブルにつながりやすくなります。
魚の目やタコができて歩行の負担に
爪の周りにできた硬い角質が靴などによる摩擦や圧迫を受けると、さらに硬く分厚くなり、魚の目やタコへと変化することがあります。
とくに魚の目は芯が神経を圧迫し、歩くたびに強い痛みを伴うため早めの対処が必要です。痛みを避けようと無意識に歩き方が変わると、姿勢が悪くなったりひざや腰など他の関節に負担をかけてしまったりと、全身に悪影響を及ぼす可能性があります。
細菌感染で腫れや膿が出るリスクも
爪周りのひび割れに細菌が侵入すると、炎症を起こし、赤く腫れたり膿が出たりすることがあります。このような症状を爪周囲炎と呼び、悪化すると爪が剥がれてしまうことがあるため注意が必要です。
自宅でできる爪周り角質ケアの手順
Step1.ぬるま湯で角質をふやかす
いきなり硬い角質を削るのではなく、まずはぬるま湯でしっかりふやかしましょう。
洗面器に40度くらいのぬるま湯を張り、5〜10分ほど指先を浸します。お風呂に入った後など、角質が柔らかくなっているときに行うのもおすすめです。
爪周りの角質が柔らかくなったら、水分を優しく拭き取ります。
Step2.爪やすりなどで優しく取り除く
角質が柔らかくなったら、専用の爪やすりやキューティクルニッパーを使って優しく取り除きます。
ポイントは「力を入れすぎないこと」。無理に削りすぎると皮膚を傷つけてしまい、余計に角質が硬くなってしまうことがあります。
爪やすりは皮膚に対して45度くらいの角度で当て、一定方向に動かしましょう。角質を少しずつ削っていくイメージです。
キューティクルニッパーは、爪の甘皮を処理する際に使用します。
甘皮とは、爪の根元にある薄い皮膚のことです。甘皮が爪にくっついていると、爪の成長を妨げたりささくれの原因になったりします。キューティクルニッパーを使って、この甘皮を優しく取り除きましょう。
Step3.しっかり保湿して清潔を保つ
角質を取り除いたあとは保湿が欠かせません。保湿を怠ると、せっかくケアした部分が再び乾燥し、角質が硬くなってしまいます。
ハンドクリームやネイルオイルを使い、指先全体と爪周りをマッサージするように丁寧に塗り込みます。とくに、爪の根元にある「爪母」という部分をマッサージすることで、健康な爪の成長を促すことができます。
注意!爪周りの角質を強く削る・むしるのはNG
爪周りの角質が気になると、つい爪や歯でむしったりカミソリで強く削ったりしていませんか。
しかし、これは逆効果です。皮膚が傷つくと修復しようとする防御反応が働き、かえって角質がさらに硬く厚くなってしまいます。
さらに、出血や感染症を招くリスクも高まります。爪周りの角質ケアで大切なのは「優しく、定期的に」 行うこと。無理に取り除こうとせず、保湿や専用ケア用品を取り入れながら少しずつ整えていくのが理想的です。
広島周辺で爪周りの角質にお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
爪周りの角質は乾燥や摩擦、栄養不足、間違った爪の切り方などが原因で起こります。「見た目が悪いだけ」と放置せず、早めに原因を理解し正しいケアを続けることが大切です。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。もし現在、広島周辺で爪周りの角質にお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!