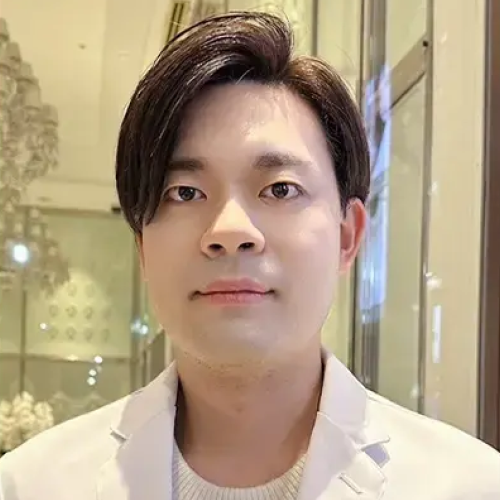手足の爪が以前より分厚くなったと感じることはありませんか?
加齢や乾燥、靴による圧迫など、さまざまな要因が重なることで、爪が硬く厚くなることがあります。変形や硬化が進むと「肥厚爪(ひこうそう)」と呼ばれることもありますが、すべてが病気というわけではありません。
本記事では、自宅で行える安全な切り方6ステップを丁寧に解説するとともに、放置によるリスクや再発を防ぐための日常的なケア方法についても詳しく紹介します。
分厚い爪・肥厚爪は自分で切ってもいいの?
結論から言うと、爪の状態によっては自分で切っても問題ありません。ただし、見た目だけで判断してしまうと、かえって状態を悪化させるおそれもあります。
たとえば、乾燥・加齢・靴の圧迫といった一時的な要因で爪が厚くなっている場合は、セルフケアでも対処できるケースがあります。このような爪は「分厚くなっただけ」の状態であり、色や形に大きな異常が見られないのが特徴です。
一方、爪そのものが変形して硬く盛り上がっていたり、白く濁ったり黄ばんでいたりする場合は注意が必要です。これらは「肥厚爪(ひこうそう)」と呼ばれ、慢性的な刺激や感染症(例:爪白癬)などが関係していることがあります。進行すると爪の内部構造が変化し、セルフケアで無理に切ると割れや出血のリスクが高まるため注意が必要です。
判断に迷ったときは、以下の点をひとつの目安にしてみてください。
- 爪が変色していないか
- 痛みやにおいがないか
- 厚みや変形が急に進んでいないか
これらに当てはまらず「うまく切れる自信がある」という場合は、正しい方法でセルフケアをおこなっても問題ありません。ただし、少しでも不安があるときは、無理に処理しようとせず、プロに相談することをおすすめします。
分厚い爪・肥厚爪の正しい切り方と注意点
ここではセルフケアが可能な範囲において、自宅でできる分厚い爪の正しい切り方を6つのステップに分けてご紹介します。注意点も一緒に確認しながら正しくケアしていきましょう。
Step1.爪を温めてやわらかくする
分厚くなった爪は水分や柔軟性を失っており、そのまま切ろうとすると割れや欠けの原因になります。まずは爪の弾力を取り戻すため、ぬるま湯に指先を浸けてやわらかくすることから始めましょう。38〜40℃程度の湯を洗面器やフットバスに張り、手や足の指先を5〜10分ほど浸けます。爪の表面がしっとりとし、爪の先を軽く押したときにやわらかさを感じられたら準備完了です。入浴後のタイミングで行うのも効果的ですが、ふやけすぎないよう注意しましょう。
Step2.厚爪専用(ニッパー)を使う
厚くなった爪には、一般的な爪切りでは歯が立たないこともあります。そこで使用したいのが、厚爪専用のニッパータイプの爪切りです。ハサミのような形状で、刃先が細く、厚みのある部分にも入りやすい構造が特徴です。使用時は、ニッパーの刃先を爪の先端に対して垂直にあて、端から数ミリずつゆっくりとカットします。一気に切ろうとせず、爪の形や硬さに応じて慎重に進めましょう。利き手でニッパーを持ち、もう一方の手で指先をしっかり固定すると、安定した動作がしやすくなります。
Step3.一度に切らず縦→横の順で少しずつ切る
厚い爪を無理に一気に切ると、ひび割れや断裂を招くおそれがあります。安全に整えるには「縦→横」の順で少しずつ切るのが基本です。まず、爪の先端を縦方向にいくつかのブロックに分けて、小さな切り込みを入れていきます。そのあとで、切り込み同士をつなぐように横方向にカットしていくと、力を分散させながら自然な形に整えることができます。無理な角度から力をかけると爪や皮膚を傷つける可能性があるため、細かく丁寧な作業を心がけましょう。
Step4.爪周りの汚れ・角質を取り除く
爪を切ったあとは、周囲の清掃も忘れてはいけません。分厚くなった爪の下やサイドには、垢や角質がたまりやすく、湿気がこもることで菌が繁殖しやすくなります。爪ブラシややわらかい綿棒などを使い、爪の下や両端をやさしくなぞるように清掃しましょう。白くこびりついた角質がある場合は、無理にこすり取らず、ぬるま湯でふやかしてからやさしく落とすのが安全です。清潔を保つことが、再発防止にもつながります。
Step5.爪やすりで形を整える
ニッパーで切った爪の先端は、鋭くとがっていたりギザギザしていたりするため、やすりでなめらかに整えることが必要です。やすりは往復させず、中央から外側へ向かって一方向に滑らせるようにかすのが基本です。
Step6.指先・爪の周りを保湿して完了
爪を切った直後の指先は、目には見えなくても乾燥しやすくなっています。保湿を怠ると再び爪が硬くなったり、ひび割れを起こしやすくなったりするため、仕上げに保湿ケアを行いましょう。尿素入りのハンドクリームやネイルオイルを用意し、甘皮周辺から爪全体、さらに指先にかけてやさしくなじませていきます。片手(または片足)につきパール粒大を目安に、小さな円を描くようにマッサージしながら塗布するのが効果的です。
分厚い爪・肥厚爪を放置するとどうなる?
分厚くなった爪を放置すると痛みや感染症、歩行トラブルにつながるおそれがあります。
最初はただの乾燥や圧迫の影響だったとしても、爪が厚くなると靴の中でぶつかりやすくなり、知らないうちに痛みや変形を引き起こすことがあります。さらに進行すると、歩くたびに違和感を覚えたり、爪の色が濁ってきたりすることも。
そして意外と見落とされがちなのが、爪の下にたまる汚れや湿気。分厚い爪の内側は通気性が悪く、細菌やカビが繁殖しやすい状態になりがちです。とくに「爪白癬(つめはくせん)」と呼ばれる爪水虫は、初期症状が目立ちにくく、気づいたときには爪がボロボロ……というケースも少なくありません。
分厚い爪・肥厚爪を防ぐためにできる対処法
爪が厚く変化してしまう前に、日常のでできる予防を意識してみましょう。日頃の工夫によって予防することも可能です。ここでは、とくに効果的な2つの対策をご紹介します。
足の爪にかかる物理的な刺激を減らす
足の爪は靴の中で日常的に押しつぶされており、とくに足先が狭い靴・ヒール・硬い素材の靴は、爪の根元を慢性的に刺激してしまいます。こうした刺激は、角質の過剰生成を促し、爪が分厚くなる引き金となるため注意が必要です。
対策としてまず見直したいのは「靴のサイズと形」です。つま先にゆとりがなく指が押し合うような靴を履いていると、爪の圧迫と血行不良を同時に招きます。理想は、指がまっすぐ伸ばせて、立ったときに足先に5〜10mmの空間がある靴を選ぶこと。
さらに、爪や指先の血流を促す目的で、簡単な足指のストレッチやマッサージを取り入れるのもおすすめです。外からの刺激を減らし、内側から循環を促すことで、厚くなりにくい土台を整えることができます。
食事から爪の成長や質をサポートする
分厚くなりやすい爪を内側からサポートするには、栄養バランスの整った食事も欠かせません。爪は「ケラチン」というたんぱく質でできているため、必要な栄養が不足すると、爪の成長や質に影響が出やすくなります。
- とくに意識したいのは、以下のような栄養素です。
- たんぱく質:爪の土台になる(卵・魚・大豆製品など)
- ビタミンB群:爪の生まれ変わりを助ける(緑黄色野菜・レバーなど)
- 鉄分や亜鉛:血のめぐりや細胞の修復を支える(赤身肉・海藻・ナッツ類など)
「きちんと食べなきゃ」と構える必要はありません。たとえば朝食にゆで卵を加えてみる、間食をナッツに変えてみるといった小さな工夫から始めてみてください。コツコツ続けることで、爪の質を内側から整える力になっていきます。
広島周辺で分厚い爪にお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
分厚くなった爪や足元の変化は見過ごしがちですが、実は早めのケアがとても大切です。違和感に気づいたときこそ、足元を見直すチャンス。
「セルフケアに自信がない」「ひとりで悩みたくない」そんなときは、「セラピストプラネット」へ気軽にご相談ください。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。もし現在、広島周辺で分厚い爪にお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!