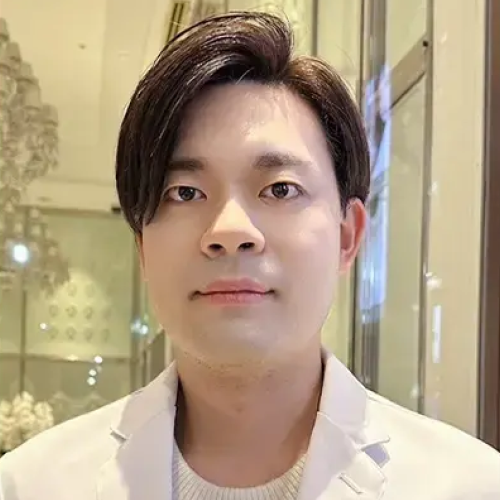爪が割れたり欠けたりする場合、体内で何らかの不調が進行しているサインであることがあります。栄養不足やホルモンバランスの乱れなど、健康上の問題が隠れている可能性も。放置すると亀裂の悪化や感染症を引き起こすリスクが高まります。本記事では、爪が割れやすくなる原因と正しい対処法を詳しく解説します。
爪が割れやすくなった?放っておくのは危険かも
爪が頻繁に割れたり欠けたりする状態は、見た目の問題だけでなく体内の不調や栄養不足のサインである場合もあります。単なる乾燥や外的刺激によるものと見過ごしていると、思わぬトラブルにつながることもあるため注意が必要です。
爪は皮膚の一部であり、健康状態が如実に表れやすい部位です。割れやすくなる背景には、鉄分やビタミンの不足・ホルモンバランスの乱れ・爪そのものの構造異常など、さまざまな要因が関係していることがあります。
また、割れやすくなった爪を放置していると亀裂が深くなって出血や炎症を招いたり、菌が入り込んで感染リスクが高まったりするケースも見られます。特に指先は頻繁に使う部位であるため、小さな損傷でも生活への支障につながりかねません。
爪が割れやすくなったときに疑うべき体の不調
まずは、爪の状態から読み取れる代表的な体のサインをチェックしてみましょう。
爪が縦に裂ける|爪甲縦裂症の可能性
爪の中央に縦の割れ目ができる場合は「爪甲縦裂症(そうこうじゅうれつしょう)」が疑われます。
日常的な衝撃や乾燥によるダメージが蓄積し、爪の中央に縦の割れ目が生じるのが特徴です。主な原因としては加齢による乾燥や手指の酷使、外的な衝撃の蓄積が挙げられます。
特に水仕事やアルコール消毒の頻度が高い生活を続けていると、爪の水分と油分が失われて亀裂を起こしやすい状態に傾きます。ネイルの除去を繰り返している方や鉄分・亜鉛などの栄養素が不足している方も注意が必要です。
爪に横線が入る|爪甲横溝の可能性
爪の表面に横向きの線や溝が現れた場合は「爪甲横溝(そうこうおうこう)」が疑われます。これは爪の成長が一時的に止まったり遅れたりした際にできるもので、爪母(そうぼ)と呼ばれる根元部分の働きが一時的に低下することで起こります。
原因は、高熱を伴う感染症・手術後の体力低下・強い精神的ストレス・過度なダイエットなど人によってさまざま。同時に複数の爪に見られる場合は、体の内側で起きている不調のサインとして現れている可能性があります。
爪が薄くてすぐ割れる|鉄欠乏性貧血の可能性
爪が全体的に薄くなり、少しの衝撃でも割れやすくなっている場合は「鉄欠乏性貧血」が関係している可能性があります。
鉄分は、酸素を全身に運ぶヘモグロビンの構成成分であり、同時に皮膚や爪の健康維持にも深く関わる栄養素です。不足すると爪がもろくなったり、平らではなく反り返るような形状(スプーンネイル)に変化するケースもあります。
こうした爪の変化に加え、慢性的な疲労感・立ちくらみ・めまいなどの不調を感じる場合は、鉄分不足を疑ってみましょう。
爪全体が割れやすい|ビタミンやミネラルの不足
爪の根元から全体にかけて薄くなり、均一に割れやすい状態が続いている場合は、ビタミンやミネラルの不足が関与している可能性があります。
特にビオチン(ビタミンB群)・ビタミンA・亜鉛・カルシウムといった栄養素は、健康な爪を形成し、強度を保つために欠かせません。これらが不足すると水分保持力が低下しやすくなるほか、角質層の再生も滞りやすくなります。
爪がもろく変形する|甲状腺機能低下症の可能性
爪全体が弱くなり、欠けやすい・反る・波打つといった変形が目立つようであれば「甲状腺機能低下症」が関係しているおそれがあります。
甲状腺ホルモンは代謝や細胞の再生を支える重要なホルモンです。このホルモンの分泌が不足すると爪の成長が鈍化し、構造にも乱れが生じやすくなります。
爪の先端が丸く反り返ったり、縦方向に波打つような凹凸が出てきたりするのが代表的な兆候です。さらに慢性的な倦怠感や体重の増加、皮膚の乾燥といった全身の不調が重なる場合は、ホルモンバランスの異常を疑ってみましょう。
爪の根元から割れる|乾癬などの皮膚疾患の可能性
爪の先端ではなく、根元付近から割れたり剥がれたりする場合は「乾癬(かんせん)」をはじめとした皮膚疾患が背景にあることがあります。
乾癬は皮膚のターンオーバーが異常に速くなることで炎症や角化異常を引き起こす疾患です。特に「爪乾癬(そうかんせん)」と呼ばれる状態では、爪の本体である爪甲(そうこう)に障害が生じ、根元から縦に裂ける・全体が白く濁る・表面に点状のくぼみ(ピット)が現れるなどの症状が見られます。
爪が白くボロボロ崩れる|爪白癬(爪水虫)の可能性
爪の色が白く濁り、表面がボロボロと崩れていくような変化が見られる場合は、「爪白癬(つめはくせん)」と呼ばれる爪の感染症が関係している可能性があります。
これは、白癬菌というカビの一種が爪の内部に入り込み、ゆっくりと爪を侵していく状態です。感染が進行すると爪が厚くなったり変色したりするだけでなく、欠けやすくなる・先端が崩れ落ちるといった症状が目立ってきます。
爪が割れやすくなるのはなぜ?日常生活に潜む原因
ここでは、割れやすい爪の主な原因を4つに分けて解説します。
栄養不足
爪の主成分は「ケラチン」と呼ばれるタンパク質で、これを構成するにはビタミンやミネラルなど多様な栄養素が必要です。特に鉄分、亜鉛、ビオチン(ビタミンB7)などの不足が続くと、爪が薄くもろくなりやすくなります。
極端な食事制限や偏った食生活を続けていると、爪の構造を維持する材料が足りず、ほんのわずかな衝撃でもヒビが入るリスクが高まります。健康な爪を保つには、バランスの取れた栄養摂取が欠かせません。
過度な乾燥
水仕事やアルコール消毒の頻度が多い方は、皮膚だけでなく爪にも乾燥による負担がかかっています。爪の水分と油分が奪われると柔軟性が失われ、パキッと割れやすくなる傾向があります。
冬場の冷たい空気やエアコンの効いた室内も、乾燥を助長する要因のひとつです。指先の保湿は手の甲だけでなく、爪の周辺まで意識して行うことが大切です。
外部からの刺激
ネイルやジェルのオフ、爪先を使った作業、頻繁な衝撃なども、爪にとっては物理的ストレスとなります。こうした刺激が繰り返されると、目に見えないダメージが蓄積され、爪が割れたり欠けたりしやすくなります。
特に硬いものを爪先でこじ開けるような動作や、爪の先端を酷使する癖がある場合は注意が必要です。見た目にはわからなくても、内部から構造が弱っていくケースも少なくありません。
加齢による爪の変化
年齢を重ねるにつれて、爪にさまざまな変化が現れます。
爪の水分や油分を保持する力が定価すると乾燥しやすくなり、爪も薄くなりがち。さらに、爪の成長速度も遅くなり、縦筋が目立つことや硬さや弾力が失われるといった症状が現れやすくなります。
これらの変化は自然な老化過程の一部であり、避けることはできません。しかし、適切なケアや保湿習慣を実践することで、その進行を遅らせ爪の健康を維持することが可能です。
今すぐできる!爪が割れたときの正しい対処法とは
まずは、「爪切り」や「爪やすり」を使って割れた爪の角をなめらかに整えましょう。
亀裂が深い場合は絆創膏やネイル用のリペアテープを活用し、爪が引っかからないよう保護することが大切です。そのうえで、爪の乾燥を防ぐためにハンドクリームやオイルで保湿を行いましょう。
洗剤やアルコールに触れる場面ではゴム手袋を着用するなど、日常生活での刺激を避ける工夫も欠かせません。爪の状態が安定するまで、無理に力をかけないよう注意してください。
割れない爪を育てる!毎日のケアと予防習慣も忘れずに
健康的で割れにくい爪を保つには、日常的なケアの積み重ねが欠かせません。
まず意識したいのが、こまめな保湿です。水仕事や手洗い後にはハンドクリームや爪専用オイルを使い、爪の乾燥を防ぎましょう。また、食生活ではタンパク質・鉄分・ビタミンB群・亜鉛など、爪の主成分となる栄養素をバランスよく摂ることが重要です。
加えて、ネイルの除去や整形は爪やすりで優しく行い、衝撃や摩擦によるダメージを防ぎます。外出時は紫外線からの保護も意識し、日焼け止めやUVカットの手袋を活用すると安心です。これらの習慣を続けることで、丈夫でしなやかな爪を育てやすくなります。
広島周辺で爪が割れやすくなったとお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
爪が割れやすくなる症状には栄養不足や乾燥、外的刺激の蓄積など、さまざまな要因が関係している場合があります。なかには、体の内側の不調や慢性的な負担が背景に潜んでいるケースもあり、放置すると悪化のリスクも否めません。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。もし現在、広島周辺で爪が割れやすくなったとお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!